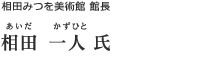子育ての秘訣
この人に聞く 連載第四回
人生の先輩の考える子育てとは(後編)

![]()
「あなたの人生最大の出会いとはなんですか?」とよくたずねます。結婚相手との出会いもあるでしょう、恩師との出会い、親友との出会いもあります。
私が思う人生最大の出会いとは親子の出会いではないでしょうか。子どもは親を選べないし、親も子どもをいつ授かるか分からない。けれども不思議なもので「しかるべき時に子どもが生まれてきて、しかるべき時に親子になる」と思います。
父も書いていますが、子どもが生まれて初めて親になるわけで、子どもがいないと親になれないので、人にとって親になると言うことは別の世界に行くことになるわけです。
そうするとどういう親子の関係が一番よいのかと考えます。それをよくあらわしているのがこの作品です。
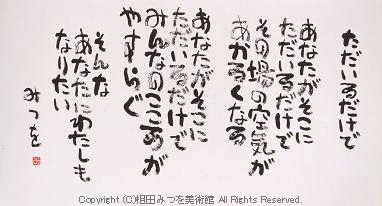
この作品の「あなた」を「お母さん」に換えて読んでみましょう。「お母さんがそこにただいるだけで 家庭の空気があかるくなる」子どもにとってお母さんは絶対的な存在で、お母さんと子どもがこのような関係になって欲しいと私は願うわけです。
お母さんと子どもがこのような関係であれば子どもの背中はあったかいと思います。伸び伸びと育っていきます。ところが最近の悲惨な事件を見たり聞いたりすると、そうではない逆の家庭が増えているのではないかという気がして仕方がありません。
「お母さんがただそこにいるだけで 家庭の空気が暗くなったり、家族みんなの心が落ち着かない」そんな家庭が増えつつあるような気がします。もしかすると父はそんなことも考えてこの詩を作ったのかも知れないと最近は考えなくもありません。
![]()
「やれなかった やらなかった どっちかな」
これについては鮮烈に嫌な思い出が残っています(笑)我が家は勉強に関しては放任で、何一つうるさく言いませんでした。ところがある夏休みのことです。とことん遊びほうけていたことがありました。宿題もなにひとつやらないで遊んでいたら、父もさすがに心配したのでしょう。
ある時三畳のぐらいの自分の部屋に遊びから帰ると、「やらなかった」の色紙がかかっていました。ぱっと見たときに真綿で首を絞められているような印象を持ちました。「さぼってないで勉強しろ」と言われるほうがまだましです。
色紙を書くことがあまりなかった父が、この言葉を色紙に書いてしかもビニールに包んでありました。だから毎日、朝晩この色紙が目に入りました。この言葉は自分への問いかけになっていて、自分で判断せざるを得ません。すると「さぼっていてやらなかった」と気づくわけです。
![]()
物心ついたときまで父親が仕事をする姿を見ていましたが、小学校に行くようになると我が家は特殊だと分かってきました。
よく「館長は相田みつをが仕事をしている姿を間近で見ていたんですよね」と言われるのですが、仕事中に筆をとった父は半径10mか20mにものすごい殺気が漂うので、おっかなくてそばに寄れませんでした。だから遠くからその姿を見ることはあっても、至近距離で筆の動きを見るようなことはなかったのです。
仕事中の父の緊迫感は自然と伝わってきて、母に仕事の邪魔をするなと言われるまでもなく、そんなことは考えもしませんでした。仕事をしている人間と言うものがどういうものか子ども心に分かり、今になっても貴重な体験だったと思います。
お勤めをしていると、疲れて帰ってきて緊張の緩んだ姿しか子どもに見せることが出来ません。何らかの形で昼間働く姿を見せることができるとよいのですが。
父の場合は優先順位が非常にはっきりしている人間でした。父の言葉に「一番大事なものに一番大事な命をかける」というのがありまして、私は子どもの頃に盛んに書いていました。父にとって一番大事なものは家族ではなくて書でした。書を中心に生活を組み立てたというのが子どもにも分かりました。一番自分が集中できて、一番気分的にも書きたい時間に書くわけです。
書を書くために広い空間が必要です。父は30畳のアトリエを持っていました。ところが家族が住んでいたのは8畳一間で、そこに一家四人が間借りしていました。友人から「30畳のアトリエを例えば20畳と10畳に分けて使えば家族が間借りすることもない」という助言もありましたが、父は頑として聞きませんでした。「仕事をするために作ったので、家族のためではない」と言うだけでした。
母は「もし父が家族のためをもっと考えていたりしたら、今の作品は残らなかったのではないか」と言っています。自分が的を絞った生き方をしなければ生きていられなかったのじゃないでしょうか。
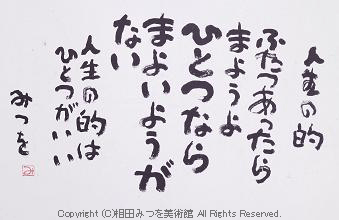

「人生の的はひとつがいい」という作品がありますが、父は書に自分のすべてをかけたのだと思います。
「育てたように子は育つ」は父が亡くなった後に、アトリエを整理していたら出てきたのです。それを見て自分の父親は私のことをそんな風に見ていたのかとしばらく感慨にふけってしまいました。けれどもそう思わない親はいないのではないでしょうか。
どちらかと言うと親の嘆きなのではないでしょうか。私の気持ちの中には「どのような道を どのように歩くとも いのちいっぱいに 生きればいいぞ」という短歌があって、これはややよそ行きな感じがありますが、本音が「育てたように子は育つ」で、この二つはペアになっていると思います。両方併せて父の子どもに対する思いがあるのでは。
佐々木正美先生(精神科医 子育て協会顧問)もよくおっしゃっていますね。親というのは「どのような道を どのように歩くとも いのちいっぱいに 生きればいいぞ」と思っていながらも、例えば進学などで「こっちの道がいい」とか「あっちの道が」という思いがあるのだ。それを踏まえた上でやっぱり「どのような道を どのように歩くとも いのちいっぱいに 生きればいいぞ」と言ってあげたいと佐々木先生も書かれています。
これもすべての親の気持ちを代弁する作品ではないかと思っています。私としてはこの二つの作品の間には相当距離があって、父はその間を行ったりきたりしながら子どもを育てたのではないかと思います。
![]()
今の世の中は殺伐として、すさんだ印象があります。子どもの頃はそういう物に染まりやすいですね。だからこそ意識的に美しいものに触れる必要があるのではないでしょうか。
難しい時代になっています。価値観も多様化していながら、世の中の空気が乾いて潤いがなくなってきているのは確か。「一生感動 一生青春」という作品がありますが、何かに感動している限りは人間の心は若々しく柔らかいということです。
特に子どもは心も身体も柔らかい時代なのに、なぜか感動するものが少ない気がします。ですから親御さんがいろんな機会を捉えて、感動する心を養うことが大事だと思います。
感情の振幅、グラデーションのない子どもが増えた気がしています。キレるという話をしましたが、無感動からいきなりキレるというような動きが多くて、何かを見てじわじわ少しずつ感動していく柔らかい心の動きが非常に少なくなっている時代になっていると思います。
善か悪か、面白いか面白くないか、いわゆるデジタル思考になっています。そういう時代だからこそアナログじゃないといけない気がするのです。
(2009年8月20日 相田みつを美術館でのインタビューから書き起こし)
鼠(2009/10/15)
文中で使用している相田みつをの作品画像は、相田みつを美術館の許可を得て使用しています。(c)Copyright All rights reserved
生年月日 |
昭和30年9月2日 |
|
詩人・書家であった相田みつをの長男で、現在は相田みつを美術館の館長を務める。 |
相田みつを美術館 |